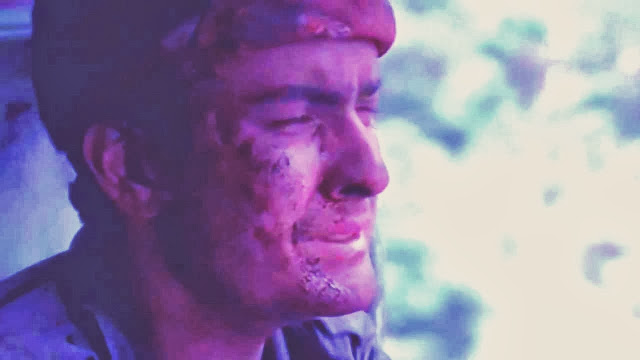 1 「悪魔」に堕ちていくハードルを低下させる、差別意識と憎悪感・恐怖感
1 「悪魔」に堕ちていくハードルを低下させる、差別意識と憎悪感・恐怖感 この存分に毒素の詰まった映画の基本骨格は、二つの異なった「大義」の衝突による、極めて現代史的要素の強い作品と考えているので、その問題意識に準拠して批評を繋いでいくつもりだが、 この辺りについての考察は後述する。
ここでは、本作の主人公・クリスの、以下のモノローグに注目したい。
1967年のこと。
「パパもママも入隊に反対して、マイホーム人生を送らせようとした。僕はパパたちの俗物主義に反発したんだよ。出世なんかしたくない。名もない平凡人でいたい。国にも尽くしたい。おじいちゃんやパパも従軍した。だから僕も志願したんだ。一兵卒としてね。兵隊はたいてい地方出身で、底辺の人たちだ。ボランスキーとかブランドンとか、聞いたこともない町から来てる。せいぜいで高卒。地元に工員の口でもあれば、マシな方だ。恵まれていない彼らが、国のために戦っている。縁の下の力持ちを自認してる。踏みつけにされて、たくましくなってるんだ。彼らこそ真のアメリカの心だ」
このクリスのモノローグから読み取れるのは、「兵隊はほとんどが地方出身、底辺の人たち」であるにも拘らず、中流階層の自分が「温室のような世界」で呼吸を繋ぐ事態に疚しさを感受し、それが大学を辞め、「志願兵」に変容するという行動心理である。
だから、「国にも尽くしたかった」と言うとき、そこに貫流する情感の中枢が「忠義」であって、「国のために戦っている」現実に関わる「大義」についての意識が、その内実をフラットな理解に留めていることが判然としている。
それ故、敵対国家への基礎知識を欠如させていたであろう、東南アジアの一角に広がる熱帯性気候下のジャングルに放たれた、中流階層出身の若者の心身が被浴した「戦場のリアリズム」の凄惨さは、戦地に着任早々、最適適応とは真逆な馴致の困難さに音を上げる始末。
「理性のない所が地獄というなら、ここがそういう所だ。来てから、たった1週間で、もうイヤになった。一番イヤなのは、先頭に立つときだ。いきなり、敵と出くわしたらどうしよう。とても疲れる」
下士官・兵卒の13人で構成される、南ベトナムの最前線の小隊(プラトーン)に配属されたクリスが、彼らの最大の敵である、ベトコン(南ベトナム解放民族戦線)の基地と疑われる村での経験は常軌を逸していた。
顔に戦闘の傷痕を残す小隊長バーンズによる、冷酷な村民殺害が惹起したばかりか、集落に火を放ち、爆弾で破壊する現実を目の当たりにしたクリスに戦慄が走る。
「お前らは、皆、ケダモノだよ」
ベトナムの少女をレイプする小隊の仲間を見て、思わず、クリスは叫ぶが、それは、エリアス軍曹の「平和主義」の無力感を晒すだけだった。
ここで、このような状況下で、人はなぜ、残酷になれるのかという厄介な問題について、簡単に言及したい。
まず、コーカソイド(白人)ではない、アジア系民族としてのベトナム人に対する差別意識が根柢にあって、そこに、自分たちの本来の敵であるベトコンへの憎悪感と、彼らがどこに潜んでいるかも知れない恐怖感、更に加えて、フランス植民地支配を打破した得体の知れない民族への怖れの感情が融合する心理が、言語も通じない眼前の、「怪しげ」な南ベトナム人の集落を射程に収めることで、追い詰めているようで、実際は「追い詰められ感」が心理的推進力となって、人間の防衛的攻撃性が爆発的に発現してしまうと、私は考えている。
差別意識と憎悪感・恐怖感。
エリアス軍曹の「平和主義」の無力感は、いつしか、一兵卒のクリスに影響を及ぼし、もう、「国
にも尽くしたい」と言わせるほどの「大義」の意識が剥落してしまっていた。これらの心理が、極限状況下で融合すれば、人間は「悪魔」に堕ちていくハードルが驚くほど低くなってしまうのだ。
デーヴ・グロスマンが 「戦争における『人殺し』の心理学」(ちくま学芸文庫)でも指摘していたように、「脱感作」、「条件付け」、「否認防衛機構」を通して、必死に防衛機制を張って生きる兵士の自我に、兵士を駆動させる相応の「大義」が張り付いていたとしても、極限状況下に捕捉された兵士とって、敵への憎悪感・恐怖感の無秩序な氾濫の中では、爆発的に発現する人間の残酷な暴走が、脆弱な観念体系の所産でしかない「大義」など、呆気なく破壊してしまうだろう。
2 「ベトナム帰還兵」としての使命感に変換されていく若者の痛切な前線経験
「この戦争は負ける」とエリアス。
「本当にそう思うのか?」とクリス。
「俺たちの国は横暴すぎたよ。罰が当たるところだ」とエリアス。
エリアス軍曹の「平和主義」の無力感は、いつしか、一兵卒のクリスに影響を及ぼし、もう、「国
「善悪の区別がつかない。除隊だけが楽しみだ」
以下、ベトコンの大攻勢の中で負傷し、搬送されていくクリスのラストモノローグ。
「今から思うと、僕たちは自分自身と戦ったんだ。敵は自分の中にいた。僕の戦争は終わった。だけど、思い出は一生残るだろう。エリアスとバーンズの反目は、いつまでも続くだろう。時として僕は、彼らの間の子のような気さえする。ともかく、生き残った僕らには、義務がある。戦場で見たことを伝え、残された一生、努力して、人生を意義あるものにすることだ」
相変わらず、言いたいメッセージをここまで台詞にしてしまう性癖は、些か情感的なイデオロギー性の過剰な作家の、その表現作品の収束点を見る思いだが、少なくとも、ここで明瞭になった点は二つある。
その一点は、エリアスとバーンズの人物造形が記号的存在性であるということ。
もう一点は、クリスが「ベトナム帰還兵」となって、反戦運動に自己投入していくということ。
これは、「ベトナム三部作」の二作目に当たる、「7月4日に生まれて」(1989年制作)で、「アンチ共和党」の情動を炸裂させたことで自明であるが、一切は、このラストモノローグのうちに語り尽くされてしまっているから、殆ど批評の余地がない。
まして、「敵は自分の中にいた」などというメッセージなど、本作を観れば誰でも分ること。
この基幹メッセージを誤読する観客に対するダメ押しの意識こそ、オリバー・ストーン監督の痼疾(こしつ)と言っていい。
「一般大衆」に対する啓蒙意識の強さは、情感的イデオロギーの過剰な作家の特色だから、敢えて異議を唱えるまでもないが、だからと言って、この映画の作品総体の訴求力は悪くないし、決して「時代限定」の映像でもないことだけは評価したい。
閑話休題。
まして、地球上のどこにあるかもよく分らない、東南アジアの低地帯に広がる落葉・半落葉の熱帯林のエリアの一角で、「自由と民主主義」を守るための戦争を継続させていくことの矛盾は、まさに、その熱帯林の地に運び込まれた若き兵士たちにとって、その心身が嫌というほど被欲する、言語に絶する苦痛以外の何ものでもなかった。
兵士たちばかりではない。
後述するが、アメリカの高官たちですら、「大義」に関わる観念体系を戦争に変換していく過程で惹起する、予想し難い事態に翻弄され、しばしば、決定的なミステイクを犯す状況の中で混乱し、右往左往していたのである。
それでも、アメリカ国民が、この戦争を継続させる「大義」の観念のうちに、彼らに特有な「マニフェスト・デスティニー」の傲慢な発想が張り付いていたと言えるだろう。
それは、決定的に不利な状況に置かれてもなお、容易に「戦争の敗北」を認知し得ないが故に、重大な決断に踏み込めない由々しき因子になっていた。
彼らにとって、「戦争の敗北」という概念は存在しないのである。
しかし、本作で描かれた兵士たちの大量の帰還が、アメリカ国内の風景を徐々に、しかし確実に変容させてしまうことによって、もはや、「自由と民主主義」という「大義」に張り付く、心地良き観念の脆弱性が決定的に露呈されていったのである。
物語に戻る。
この物語の基本骨格を要約すれば、以下の文脈に収斂されるだろう。
即ち、相応の「大義」と愛国心を抱懐する普通の若者が、寸分の「大義」も拾えない小隊での、極限状況下の前線の渦中の苛烈な経験を通して、拠って立っていたはずの「大義」と愛国心の脆弱性を感受することで、能動的に自己投入していった「正義」の戦争の内実が、「内部戦争」であったという爛れ切った現実の認知に至る、シビアな心的行程を抉り出したこと ―― この把握に尽きる。
敢えて類型的に、「善」(エリアス)と「悪」(エリアス)を作り出したことで、本作の主人公の若者・クリスの心の振れ幅をフォローし、その心的行程の変容を映し出していく。
従って、そんな普通の若者を、除隊の日への希望のみを繋ぎ、ドラッグによって自我を感覚鈍麻させる「非日常」を常態化していて、そこに寸分の「大義」も拾えない小隊に放り込んでいく。
これが、基幹モチーフの起動点と化すと言えるのは、そんな小隊内部での苛烈な経験を通して、件の若者が、学習的に何を手に入れ、何を失っていったかという作り手の問題意識が、小隊内部の人物造形のうちに鮮明に具現化されていたからである。
言うまでもなく、この小隊内部のうちに造形されたのは、「善」(エリアス)と「悪」(エリアス)の記号的存在性である。
敢えて類型的に、「善」(エリアス)と「悪」(エリアス)を作り出したことで、本作の主人公の若者・クリスの心の振れ幅をフォローし、その心的行程の変容を映し出していく。
そのことによって、ベトナム戦争の本質を剔抉(てっけつ)すること。
この点に、本作の問題意識が読み取れると、私は考える。
では、「善」(エリアス)と「悪」(バーンズ)の、その記号的存在性の内実とは何だったのか。
「戦争には、守るべき最低限の倫理規範がある」
これが、「善」(エリアス)の記号的存在性の意味であるのに対し、「悪」(バーンズ)の場合は何だったのか。
「戦争には、殺るか殺られるかの戦闘のリアリズムしかない」
この一点に尽きるだろう。
そればかりではない。
(人生論的映画評論・続/プラトーン(‘86) オリバー・ストーン <「ベトナム帰還兵」としての使命感に変換されていく若者の痛切な前線経験>)より抜粋http://zilgz.blogspot.jp/2014/01/86.html